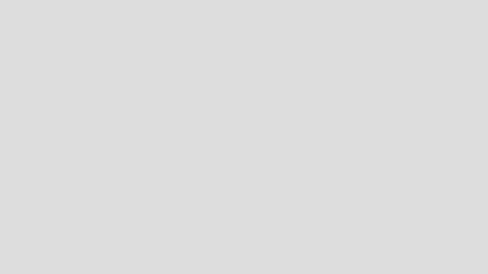大阪で100年以上愛されてる幸運の神様!ビリケンさんについて
公開日:2021.11.01 更新日:2022.11.16

幸運を呼ぶ福の神として、大阪人に古くから愛されてきた「ビリケンさん」をご存知でしょうか。
今回の記事では、商売繁盛から縁結び、合格祈願、必勝祈願、家内安全まで、庶民の様々な願いを叶えてくれると言われるビリケンさんについてご紹介します。

株式会社MEBUKU
Pokke編集部
👇こちらの記事もおすすめ
観光もグルメも満喫できる街!大阪府のおすすめお宿10選
1.大阪のシンボル通天閣「ビリケンさん」とは?
大阪を代表するディープタウン新世界のシンボルであり、国の登録有形文化財にも指定された「通天閣」。
その5階にある展望台で、観光客を真っ先に出迎えてくれるのが幸運の神様ビリケン像、通称「ビリケンさん」です。
怒っているのか笑っているのか分からない愛嬌のある表情と、足を投げ出して座っているふてぶてしさが特徴のビリケンさん。
見た目の印象から「妖怪?」と思っている人も多いようですが、台座に「THE GOD OF THINGS AS THEY OUGHT TO BE(万事あるがままの神)」と書かれている通り、実はあらゆる願いを叶える霊験あらたかな全知全能の神様なのです。
足の裏を撫でるとご利益があると言われているため、連日多くの人が、わざわざ足の裏を撫でるために通天閣を訪れています。
また、一般の商店や民家に祀られることも多く、大阪では身近な福の神として庶民の暮らしを見守っています。
2.実はアメリカ生まれ!ビリケンさんの由来について
大阪の福の神として根付いているビリケン像ですが、元々はアメリカの女流美術家フローレンス・プリッツが、「夢の中で見た神様」をモデルとして1907年頃に作った作品です。
プリッツ自身が「自分の前世は日本人だったに違いない」と語り、和服を着た写真も残っている程の親日家なので、日本人が親近感を覚えるビリケン像のルックスも、そんな彼女の想いが反映されたのかも知れません。
後にシカゴの企業ビリケンカンパニーが像などを制作・販売し、「幸福の神様」として全世界に知れ渡るようになりました。
日本伝来は1909年頃で、花柳界を中心に縁起物として流行。そして1912年に通天閣と同時開業した遊園地に「ビリケン堂」が作られ、初めて新世界にお目見えしました。
その後、像が行方不明になったり、通天閣が火災に遭うなど紆余曲折はありましたが、1979年に2代目ビリケンさんが通天閣で復活。30年以上にわたって通天閣名物として愛されました。
そして2012年5月、通天閣・新世界100周年を機に3代目へとバトンタッチされ、現在に至っています。
3.知る人ぞ知る豆知識!ビリケンさんの3つのトリビア
3-1 古き良き名画のワンシーンを彩ったビリケン像
1940年公開のアメリカ映画『哀愁』では、戦地へ向かう恋人ロバート・テイラーの無事を祈って、ビビアン・リーが幸運のお守りとしてビリケン像を手渡すシーンがあります。
映画の冒頭でも男がそのやりとりを回想するシーンが描かれるなど、物語の鍵を握る重要な小道具となっていました。
3-2 映画の主役としても活躍したビリケンさん
1996年公開の日本映画『ビリケン』は、タイトル通り幸運を呼ぶ神様・ビリケンの活躍を描いたファンタジーコメディ。
主役のビリケンに杉本哲太、マドンナ役は山口智子、そして岸部一徳、泉谷しげる、原田芳雄、國村隼が脇を固めるという豪華なキャスティングでした。
3-3 アメリカでは名門大学のマスコットに
1818年創立のセントルイス大学は、ミシシッピ川以西では最も古い名門大学ですが、ビリケン像は通天閣だけでなく、同大学の公式キャラクターでもあります。
キャンパス内には「THE BILLIKEN」と題したビリケン像が立てられており、学内の全てのスポーツチームが「ビリケンズ」を名乗っています。
4.幸運を呼ぶ!ビリケンさんグッズあれこれ
通天閣の売店では、幸運をもたらすビリケングッズが人気です。ちょっとしたお土産には、金と銀のビリケンさんがペアになった「ストラップ・キーホルダー」や、幸福をピタッとくっつける「マグネット」がおすすめ。
小判の真ん中にビリケンさんが浮き彫りにされた「金運小判」や「お守り」も、いかにもご利益がありそうで喜ばれるかも知れません。
本気でご利益にあやかりたいなら、高さ48cm、重さ8kgの「ビリケン置物(特大)」はいかがでしょう。12,960円(税込)と少々値は張りますが、玄関先に置くとインパクトは抜群です。
その他にも「靴下」や「ボクサーパンツ」、「やわらかマスコットキーホルダー」などが人気のアイテムとなっているようです。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。新世界では通天閣の展望台だけでなく、かつて初代が祀られていた「ビリケン堂」の跡地に建つ「ビリケン神社」でも、ビリケンさんの足の裏を撫でたり掻いたりしながら願い事ができます。
「日本一の串かつ横綱」のド派手な看板があるビルの1階にあり、つい見落としてしまいそうになる小さな神社ですが、通天閣のビリケンさんと掛け持ちすればご利益が倍増するかも知れません。
新世界へお出かけの際はぜひお試し下さい。
👇【保存版】大阪の読んでおきたい記事3選
観光もグルメも満喫できる街!大阪府のおすすめお宿10選
大阪の日持ちするお土産18選!甘いお菓子からしょっぱい物まで
大阪の夜を満喫するならココ!目的別おすすめスポットを紹介
シェアしよう
大阪のブログ
一覧で見る大阪の音声ガイド
一覧で見る大阪のショッピング
一覧で見る共有
https://jp.pokke.in/blog/7452