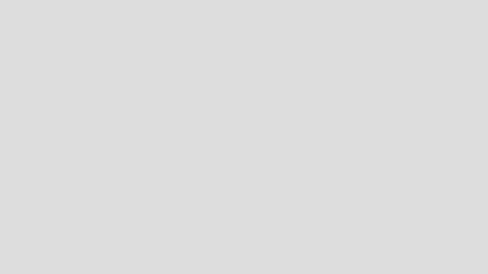カステラのルーツを探れ!長崎伝来は本当?歴史や由来も紹介
公開日:2021.10.21 更新日:2023.09.28

本記事内にはアフィリエイト広告を利用しています
カステラは、15世紀から16世紀にかけて日本を訪れた、ポルトガルの貿易商人やキリスト教の宣教師によって伝えられたと言われています。
そこで、今回の記事ではカステラという名前の由来や歴史など、長崎を中心に国内に広がったカステラのルーツを追いかけてみましょう。

株式会社MEBUKU
Pokke編集部
👇こちらの記事もおすすめ
長崎でおすすめのホテル10選!大人の贅沢旅を満喫するならここ!
1.カステラの歴史を探ろう!名前の由来はどこから来たのか
そもそもカステラという名前はどこからきたのでしょうか。その由来を探ってみます。
カステラの名前の由来①「カスティーラ王国説」
カスティーラ王国とは、1035年から1715年までイベリア半島中央部(現スペイン)で栄えた王国でした。そこで生まれたお菓子がカステラという名前の由来だとする説です。
日本を訪れていたポルトガル人が、「このお菓子はなんと言うのか」と問う日本人に対し、「カステラ王国のお菓子だ」(ボロ・デ・カステラ)と答えたそうです。
それを聞いた日本人が、「このお菓子はカステラと言うのですな」と勘違いして、カステラと言う名前が広がったというものです。
カステラの名前の由来②「カスティーリョ(スペイン語の城)説」
もう一つの説は、スペインでお菓子を作るときにメレンゲをしっかりとあわ立て「お城のように高くなれ」と掛け声をかけたそうです。
お城のことをスペイン語で「カスティーリョ」と言い、その言葉が耳に残ってカステラと言うようになったというものです。
2.カステラ発祥の地とは?
それでは、カステラと呼ばれるお菓子のルーツはどんなものだったのでしょうか。
カステラ発祥の説①「ポルトガルのパン・デ・ロー」
ポルトガルの各地で「パン・デ・ロー」と呼ばれるふっくらとした焼き菓子が盛んに作られていました。これが日本のカステラの原型ではないかとされています。
カステラ発祥の説②「スペインのビスコチョ」
もう一つはスペインで船に乗せる食料の乾パンとして作られていた「ビスコチョ」が原型だとするものです。当時はスペイン海軍の保存食として用いられてきました。
3.いつ誰が日本へ持ち込んだ!?カステラの伝来とは
カステラの原型となったお菓子は、いつ誰が日本へ持ち込んだのでしょうか。1494年にイベリア半島はポルトガル王国とカスティーラ王国の二つが領土を分け合っていました。
ポルトガルは喜望峰を回って東から、カスティーラ(スペイン)王国は南米ホーン岬を回って西から日本にやってきました。
これらの国の貿易商人やキリスト教の宣教師たちによってカステラは日本にもたらされたと言われています。
カステラの伝来①「長崎初上陸説」
イベリア半島を出発した一行は、西から東から地球を半周して種子島、鹿児島、平戸を経て長崎へと到着しました。
1570年には長崎が当時唯一の外国貿易港として開港され、翌年には初のポルトガル船が入港しています。つまり、当時は長崎が唯一外国に開かれた港だったのです。
カステラの伝来②「平戸初上陸説」
実は地元でまことしやかにささやかれている噂がありました。カステラは長崎より先に平戸に伝えられ、平戸で今も作られている「カスドース」がカステラの完成形だと言うのです。
「カスドース」とは、簡単に言えばカステラのフレンチトーストのようなもので、長崎のカステラはカスドースの未完成品だそうです。
残念ながら確証は全くありませんが、平戸にポルトガル船が初入港したのが1543年、長崎への初入港が1571年なので平戸初上陸説の可能性は否定できません。
4.一度は食べて欲しい!長崎カステラの名店を紹介
最初に伝わったカステラの製法は、小麦粉・砂糖・卵を全て同量に配合して混ぜ合わせ、蒸し焼き鍋で焼くというものでした。
その後、江戸時代になって材料や配合が変化し、鍋の性能も良くなり現在の形が出来上がりました。
カステラの名店①「福砂屋」
1624年(寛永元年)創業の福砂屋は「カステラ本家」と言う登録商標を持つ老舗です。創業以来、手作りにこだわって添加物を一切加えないことから、賞味期限が9日前後と短いのです。
特徴はふんわりとした触覚を生み出す、「別立法」と呼ばれる卵の泡立て方法。
黄身と白身を別々に泡立ててから混ぜると言うもので、泡立ったメレンゲを見て「お城(カスティーリョ)のように高くなれ」と叫んだかどうかは定かではありません。
カステラの名店②「松翁軒」
1681年(天和元年)創業の老舗が「松翁軒」です。最初に伝来した製法に水飴を加えるなど、創意工夫を加えて独特の和菓子として生まれました。
明治になってチョコレートを加えた「チョコラーテ」を作り出し、明治33年のパリ万博に出品したカステラが賞を受けるなど世界的に高い評価を得ました。
5.長崎以外の面白い名物カステラ
長崎で盛んに作られたカステラは、17世紀後半には日本中に広まっていました。1719年(享保4年)に書かれた資料には長崎土産としてカステラと言う名前が出てきます。
また、外国の情報が入る唯一の街として多くの若者が長崎に集まり、彼らが帰国時に製法を持ち帰ったことで全国へと広がりました。
全国に広がったカステラの中から、江戸時代から作られている名品を2つご紹介します。
面白い名物カステラ①「秋田の豆腐カステラ」
あまりなじみのない「豆腐カステラ」ですが、実は江戸時代から秋田県南部の郷土菓子として親しまれてきました。
当時は砂糖や卵という貴重品を使っていたことで、冠婚葬祭など特別な日の振る舞い菓子として用いられていました。
戦後になってスーパーなどで販売されるようになったのですが、なぜカステラと言う名前がついたかは不明です。
江戸時代に盛んだった北前船によって長崎のカステラの情報が伝わった可能性があります。
面白い名物カステラ②「京都のカステイラ」
江戸時代末期、初代が長崎で修行し創業した、全国でも珍しいカステラの専門店が京都の「越後家多齢堂」です。
材料や配合などは創業当時から変わらず守り続け、砂糖や卵をたっぷりと使ったカステラは「カステイラ」と呼んでいます。
ここも福砂屋と同じく全く添加物を使っていないことで、賞味期限も3〜5日程度だそうです。
6.まとめ
カステラは和菓子だということをご存知でしょうか。明治時代以降に西洋から日本に入ってきた西洋菓子を洋菓子と呼び、室町時代に日本に入ってきたカステラは和菓子と分類するからです。
しかし、そのルーツを探ってみると、洋菓子として出発し長い時間の中で日本独自の創意工夫によって、和菓子として発達してきた歴史がありました。
カステラの歴史をひもときながら、長崎という小さな窓から世界を眺めた当時の人々の想像力の豊かさを感じました。
👇【保存版】長崎の読んでおきたい記事3選
長崎でおすすめのホテル10選!大人の贅沢旅を満喫するならここ!
長崎の名産といえば!お菓子や果物、お土産について徹底紹介
旅行の記念におすすめ!長崎で買いたい雑貨、小物のお土産20選
シェアしよう
長崎のブログ
一覧で見る長崎の音声ガイド
一覧で見る長崎のホテル
一覧で見る共有
https://jp.pokke.in/blog/6762