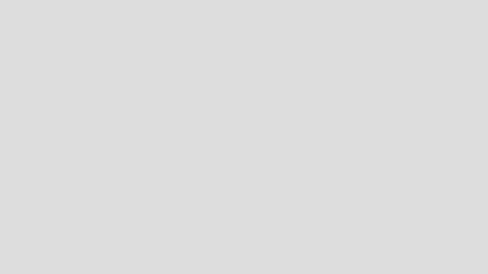5分で理解できる!奈良の名園『依水園』の簡単見どころまとめ
公開日:2021.11.01 更新日:2022.11.25

奈良にある数ある観光地の中で、東大寺に並んで、外国人観光客に人気があるスポットが、名勝依水園です。
なぜ、依水園がそんなに人気が高いのがご存知でしょうか?
アメリカの日本庭園専門雑誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」誌が選ぶ日本庭園ランキングで堂々の7位にランクインしているからです。
依水園とその魅力をわかりやすくまとめてみました。

株式会社MEBUKU
Pokke編集部
👇こちらの記事もおすすめ
歴史を感じる古都の街!奈良県のおすすめホテル10選
1.奈良の名園『依水園』がある場所とは?
依水園は、奈良観光の中心、東大寺南大門の真西にあります。依水園は、その地を流れる吉城川の流れをうまく取り入れて、庭をつくっています。
依水園のある場所は、奈良市水門町です。その地名のもととなった水門こそ今では見られませんが、かつて吉城川にはいくつもの水門が設けられ、水車の原動力となっていました。
昔は、依水園の辺りで、川の水と水車を、製粉業や晒し業に利用してきました。
依水園の池の周りには、臼(うす)に使われていた石が飛び石として使われ、園内には水車小屋もあり、当時をイメージすることができます。
2.依水園は誰がつくったの?
依水園は、前園、後園の二つに大きく分けられます。それぞれは、つくられた時代が違います。
前園は誰がつくった?
前園は、江戸時代前期に奈良晒(ならざらし)を扱う御用商人だった清須美道清が吉城川のそばでお茶をたのしむため、別邸として三秀亭を他の場所に移して建てたのがはじまりです。
奈良晒ってそもそも何かご存知でしょうか?
奈良晒とは、武士の裃(かみしも)などに使う高級麻織物のことで、先ほども書きましたように吉城川の川の水を利用してつくっていました。
奈良晒は、室町時代からつくられていましたが、徳川幕府の御用達品となってその名声が広まり、御用商人であった清須美家には莫大なお金が集まりました。
後園は誰がつくった?
後園は明治時代に、呉服商でならまち7人衆といわれた実業家、関藤次郎が吉城川の水を引いて、茶の湯と詩歌の会をたのしむために築山式の池泉回遊式庭園をつくりました。
庭をデザインしたのは、茶道裏千家の十二世又妙斎宗室です。
つまり、依水園は、江戸時代と明治時代に奈良の地で財を成した商人、実業家が贅沢をするためにつくった庭園ということになります。
3.依水園をなぜつくったの?
依水園の東隣に同じ日本庭園の吉城園があります。
江戸時代に清須美道清が依水園の前園をつくるまで、依水園前園と吉城園は、興福寺のわき寺、摩尼寿院(まにじゅいん)の庭園だったと言われています。
また、奈良は、現在行われている茶道の原形が起こった地とされています。
摩尼寿院のあたりは、この茶道の発展を育んだ地であり、依水園、吉城園は、茶道発祥に深く関わっています。
そのような地に、時めく商人が、自分のための茶室を建てよう、庭をつくろうと思うのは、自然なことでした。
その後、1939年、海運業で財をなした中村家が依水園を買い取ります。1969年には、中村家所蔵の美術品を展示、公開するため、寧楽美術館が園内に建てられました。
4.最大限楽しむために!依水園の見どころを紹介
依水園の見どころ①「前園」
清須美道清によって移築された三秀亭の前の池には、鶴亀をなぞらえた中島をつくり、池の周りには灯篭が品よく置かれています。
池の護岸の石組みは、江戸時代の庭園の特徴をよく表しています。
三秀亭では、前園を見ながら、昼食や抹茶をいただけます。都会の真ん中にありながら、鳥の鳴き声の他には何も聞こえないような静けさの中でおいしい料理をいただけるのは、最高の贅沢であるように思います。
依水園の見どころ②「後園」
園内に建てられた建物の間の通路を抜け、狭い石畳を抜けると、一気に視界が開けます。
遠くに見える若草山をはじめ、春日奥山や御蓋山(みかさやま)、近くに見える東大寺南大門を借景としています。
はるかに広がる空間と池に映る青空を取り込んだ、息を飲むような美しい庭園です。
氷心亭(ひょうしんてい)は、新薬師寺に使われていた天平時代の古材を天井板などにつかった明治時代の書院造の茶室です。ここでは、後園を見ながら抹茶をいただけます。
依水園の見どころ③「寧楽美術館(ねいらくびじゅつかん)」
中村家3代が集めた、神戸大空襲を免れた二千数百余点を所蔵しています。
古代中国の青銅器や拓本、高麗・朝鮮王国の陶磁器、日本の茶道具など、定期的に展示入れ替えを行っています。
依水園の見どころ④「季節の花々」
2月の椿に始まり、3月はアセビや紅梅。
4月は、桜やツツジ、5月は藤や菖蒲、カキツバタ。
6月は、菖蒲やスイレン、7月はハス。
8月は百日紅、10月は萩。
11月は紅葉、12月山茶花と一年を通じて、お花を楽しめます。
とくに、5,6月の菖蒲、秋の紅葉は見ごたえたっぷりです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。依水園の魅力が伝わったでしょうか。
依水園には、日本語や英語、中国語のボランティアガイドの方がおられて、熱心に説明してくださいます。
そして、依水園のまわりは、奈良らしい静かなたたずまいのところです。
有名なお蕎麦屋さん(喜多原)や、工場跡地のカフェ(工場跡事務所)などが近くにありますから、ぜひ、訪れてみてください。
👇【保存版】奈良の読んでおきたい記事3選
歴史を感じる古都の街!奈良県のおすすめホテル10選
奈良だから買いたいお土産30選!人気のお菓子から雑貨まで紹介
奈良検定1級ホルダーが教える!奈良で食べたいおすすめグルメ
シェアしよう
奈良のブログ
一覧で見る奈良のグルメ
一覧で見る共有
https://jp.pokke.in/blog/7569