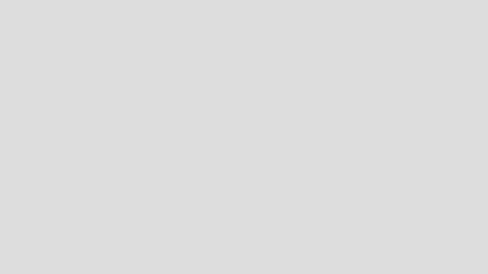川床とは?「かわどこ」と「ゆか」にこめた京都人の愛について
公開日:2021.10.21 更新日:2022.11.08

川床(かわどこ)の予約電話に「ゆかでよろしいか」と聞き返す京都人。“いけず”なイメージに聞こえますが、実はそこには京都人特有の地元愛が込められているのをご存知でしょうか。
「川床」発祥の地京都の歴史と文化に裏打ちされた自信が、「ゆかと呼んで欲しい」という思いとなって口からでてしまうのです。
では、そもそも「川床(ゆか)」はいつ頃から始まったのでしょうか。歴史や言葉の違いから、おすすめの店、時期なども含めてご紹介しましょう。

株式会社MEBUKU
Pokke編集部
👇こちらの記事もおすすめ
京都旅行を極上にする高級旅館。おすすめの宿10選
1.川床とは?
京都鴨川納涼床、いわゆる川床もあと3日ほどになりました。最近肌寒くなりましたもんね。川床はまた来年。
2018.9.27 撮影 pic.twitter.com/Rza11Psm7G
— MKタクシー (@MKofficial_PR) 2018年9月27日
鴨川納涼床は夏の京都の風物詩です。たくさんのお料理屋さんが川の上であったり、屋外で川のよく見える場所に座敷を作ったりして料理を楽しむことです。
鴨川右岸沿いにずらりと並ぶ様子に、暑い夏をなんとか涼しく過ごそうとした京都人の知恵が息づいています。
「川床(かわどこ)」とひとくちで言えば京都だけの専売特許ではありません。清流の上に床を設けて、食事をするのはどこででも見かける風景です。
ところが、「川床」と聞いてと京都をイメージする方が多いのは、その長い歴史と鴨川で磨かれた京都文化への憧れがあるのかもしれません。
2.川床の歴史について
応仁文明の乱など長い戦乱が終わり、豊臣秀吉によって平和な時代が訪れました。秀吉による三条や五条橋の架替えから始まった鴨川整備。
裕福な商人たちが河原に床几(しょうぎ)を持ち出しにぎわいを見せ始めました。
江戸時代になり歓楽街や花街が更に整備され、鴨川沿いには400軒を超える茶屋があふれ、張り出し式の床机を並べた「河原の涼み」と呼ばれる文化が生まれました。
明治時代になってからは祇園会(祇園祭)の行われる7・8月に床を出すのが定着し、河川の改修や電車の延伸などによって、現在と同じ西側(右岸)だけの川床(ゆか)となっています。
3.「ゆか」と「かわどこ」の違いについて
京都で「川床」と書くと「鴨川納涼床」「貴船の川床」が有名です。京都では鴨川納涼床のことを「ゆか」と呼び、貴船では「かわどこ」と呼び習わしています。
理由については諸説あるようですが、鴨川では江戸時代にすでに「床」を「ゆか」と呼んでいたそうです。
貴船で納涼床が始まったのは、大正時代頃からだと言われ、鯖街道の道中で休憩場所として料理を提供したのが始まりです。
呼び名については、鴨川と違いを出すために「かわどこ」と呼ぶようになったという説や貴船の位置が京都の床の間にあたるので「床(とこ)」にちなんだと言う説などがあります。
4.京都のおすすめ川床!ぜひ一度訪れてみよう
鴨川納涼床には約100軒、貴船の川床には約20軒のお店が並びます。どこを選べばいいのか悩んでしまいますが、江戸の風情と京都の文化を堪能したいなら、少し高価ですが老舗の料理店を選びましょう。
椅子やテーブルもいいですが、やはり座敷机に座布団でどっしりと腰を下ろし、清流の音や山の緑に癒やされながら、ちょっぴり大人の夏を楽しむのがいかにも京都らしいと思いませんか。
4-1 鴨川納涼床「京料理 本家たん熊 本店」
鴨川と高瀬川にはさまれた木屋町仏光寺の角に、京懐石とすっぽん料理の老舗「たん熊」があります。京都の風情を心から味わって欲しいと、しつらえられた調度品の数々。
四季折々の気遣いも感じられます。お出かけの際にはちょっぴりフォーマルな装いが素敵です。
4-2 貴船の川床「貴船ふじや」
貴船で「川床(かわどこ)」を最初に始めたのが「貴船ふじや」の先々代でした。最初はお茶を飲みながら涼むといった程度だったのですが、現在のように床になったのは戦後だそうです。
創業は江戸末期の天保年間、以来新鮮な川魚一筋で愛され続ける老舗です。
5.川床を楽しむなら9月が最高
京都の暑い夏を涼しくしたいと知恵を絞って生まれた「川床」ですが、いくら川の上とはいえ真夏はやはり暑いです。そこで「川床」を楽しむ時期としてオススメは9月。
夏の暑さも一段落し、川面を吹き抜ける風が心地よく感じる時期にこそ、「川床」を心から楽しむことができます。ちなみに、鴨川納涼床は毎年5月1日から9月30日まで設営されます。
6.最後に
「ゆか」と言っても「かわどこ」と言ってもどちらでも大丈夫ですが、ちゃんと区別をすると“いけず”な京都人に一目置かれるかもしれません。
多くの方が京都を訪れ、京都の文化や風情を味わってほしい、「川床」という夏の風物詩を堪能してほしいと思う、京都人の心は一つです。
夏のひと時、暑気払いを兼ねて「川床」で京料理に舌鼓を打つ贅沢を味わってみましょう。
👇【保存版】京都の読んでおきたい記事3選
京都旅行を極上にする高級旅館。おすすめの宿10選
京都のおすすめ名産品!食べ物やスイーツ、工芸品も徹底紹介
京都らしさが溢れる貴族の別荘地!嵐山おすすめ観光スポット7選
シェアしよう
京都のブログ
一覧で見る京都の音声ガイド
一覧で見る京都の観光施設
一覧で見る共有
https://jp.pokke.in/blog/6867