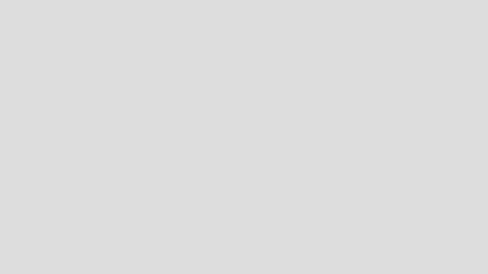B級グルメとは?A級グルメとの違いやおすすめ人気グルメも紹介
公開日:2021.10.21 更新日:2022.11.08

「B級グルメ」という言葉はよく聞き、それを目当てに旅行している人も多いことでしょう。
全国にB級グルメが乱立状態の昨今ですが、そもそもB級グルメとはどのようなものなのでしょうか。また、B級があるならA級やC級もあるのでしょうか。
今回の記事では「B級グルメ」についてわかりやすくお伝えします。

株式会社MEBUKU
Pokke編集部
B級グルメとは?この言葉が使われるきっかけを紹介
「B級グルメ」とは、価格が安く、食材も贅沢なものではないのに美味しい、庶民的な料理のことです。
1985年頃から使われ始めた言葉で、当初は香川の讃岐そば、神戸の明石焼き、東京月島のもんじゃ焼など、比較的昔からその土地にある伝統的なご当地料理を指していました。
ところが「B-1グランプリ」が開かれるようになった2006年頃から、創作的な意味合いが強くなって来て、伝統的なものではなくても、その土地の食材を使ったリーズナブルな料理なら「B級グルメ」であるという概念が広がり、それを地域おこしに活用しようという風潮が広まりました。
「B級グルメ」という言葉が普及するにつれ、従来の「伝統的な」とか「地域のために」という意味合いが薄れ、「業界のため」「店のため」という風潮が一部で見られるようになってきたのも事実です。
特に安易に地域の特産品を入れた「ご当地焼きそば」や「ご当地カレー」は乱立気味です。
B級グルメがあるのであれば、A級やC級もあるの?
「B級グルメ」があるならA級やC級のグルメもあるのでしょうか。
A級グルメってある?
「A級グルメ」という言葉は、もともとは2010年に、ある雑誌の編集長が「雪国A級グルメ」という言葉を創出し、明文化したものです。
コンセプトは新潟県を中心に「安全性に配慮した雪国の伝統の料理」を継承していこうという、ごく狭義で使われていた言葉なのです。
「A級グルメ」は、現在では地産地消的な意味合いをもって全国に広がっています。つまり「地域の特産品や名産品としてブランド化され、有名かつ高価で、あまり他地域には出回らないもの」という定義です。
このように元来「A級グルメ」は「B級グルメ」の対義としての言葉では全くないのですが、実際は「B級グルメ」より上の「高級で手の込んだ料理」という意味で、高級レストランで食べる料理などのことを指して「A級グルメ」という言葉を使う人の方が多いようです。
C級グルメってある?
「C級グルメ」という言葉はまだまだ普及はしていませんが、自虐的あるいは謙遜の意味も含めて「C級グルメ」を自称する人たちがいます。
この場合でも「B級より下」というわけではなく、ややキワモノ、普通は食さない、といった意味に使われることが多いようです。
例えば、八王子のパンカツ(パンに水で溶いた小麦粉とパン粉をつけて、油をひいた鉄板の上で焼き、ウスターソースをかけたもの)は「C級グルメ」を自称しています。
東北のある地区ではドジョウやジビエ(獣肉)など、一般的ではない地域の食材を使ったものを「C級グルメ」として売り出そうという計画があるようです。
有名B級グルメを厳選!知っておくべきおすすめ5選
有名B級グルメ①「佐世保バーガー(長崎県)」
佐世保バーガーうんめえ〜! pic.twitter.com/oadGE7vd5i
— ゴリラ (@thekamakiri) 2018年9月6日
軍港があった佐世保には戦後進駐軍が駐留し、ハンバーガーがもたらされました。
B級グルメとして有名な「佐世保バーガー」は、佐世保市内の店で提供される「手作り」で「作り置きをしない」こだわりのハンバーガー全般を指す言葉で、特に決まった具材やスタイルがあるわけではありません。
有名B級グルメ②「ほうとう(山梨県)」
これが山梨のほうとう!
麺がめっちゃモチモチしてた( ^ω^ ) pic.twitter.com/uB8UiIYSw3— 讃岐@北陸東海遠征中 (@kaleid0728) 2018年9月7日
小麦粉で作った麺を、野菜やカボチャの入った味噌仕立ての汁で煮込んだ「ほうとう」は、山梨県の鍋料理です。
平太麺で作られるのがオリジナルで、周辺地域にも似たような郷土料理が見られます。
有名B級グルメ③「ソースかつ丼(福井県)」
ソースかつ丼って各地でご当地メニュー的な立ち位置にいる気がする。福井とか会津とか… これは駒ヶ根(伊那谷)。 pic.twitter.com/pyX58kvt0t
— のりよし (@gty_nu) 2018年9月5日
福井県の「ソースカツ丼」は、ご飯の上に揚げてウスターソースベースのタレに漬けたカツを乗せたものです。
見た目のインパクトと美味しさ、そして十分な食べごたえですっかり有名になりました。ソースは店それぞれに秘伝の味があります。
有名B級グルメ④「金沢カレー(石川県)」
金沢カレー pic.twitter.com/rNvjpXc9Ui
— 【高画質】飯テロ (@mesitero_umai) 2018年9月1日
「金沢カレー」は、カレーライスの上に揚げたカツを乗せたものですが、いくつかの特徴があります。まず、ルーはドロッと濃厚でやや甘めです。
盛り付ける皿はステンレスの平皿で、ライスが見えないようにルーをかけます。カツにはソースがかかっていて、付け合わせのキャベツも一皿に盛ります。
先の割れたスプーンで豪快に食べるB級グルメです。
有名B級グルメ⑤「じゃじゃ麵(岩手県)」
岩手のローカルフード、じゃじゃ麵。素朴で美味い! (@ 白龍 本店 in 盛岡市, 岩手県) https://t.co/mvvdP6x4lI pic.twitter.com/Eeag5ci9iz
— Yoshinobu Takagi (@nobu1080) 2015年6月14日
「じゃじゃ麺」は盛岡市のB級グルメで、平うどんに肉みそときゅうり、ネギを乗せたものです。おろししょうが、にんにく、辛味などを加えて自分好みの味にして食べます。
麺を食べた後は、生卵と麺のゆで汁を入れてスープにして食します。ひつまぶしのように変化を楽しめる一品です。
最後に
以上、B級グルメについての解説と、知って欲しい有名B級グルメ5選をご紹介しました。
近年乱立気味のB級グルメではありますが、それぞれに地域のアイディアと、その土地ならではの食材が盛り込まれています。
B級グルメを食することは、その土地を知ることにもつながります。どこかに観光に行く時は、是非その地のB級グルメにも目を向けてみてください。
シェアしよう
佐世保のグルメ
一覧で見る共有
https://jp.pokke.in/blog/6918