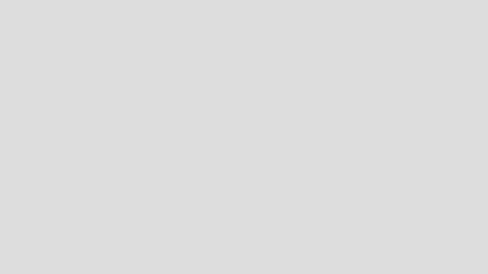おみくじはなぜ結ぶの!?おみくじの種類や結ぶ理由なども紹介
公開日:2021.11.16 更新日:2022.11.25

おみくじを引いた後、そのおみくじをどうしたら良いのか悩んだことはないでしょうか。初詣などで、神社や仏閣に訪れて占った後、どうすればいいか迷ってしまいますよね。
今回の記事では、おみくじは枝などに結ぶのか?持ち帰ればいいのか?など、おみくじの気になる疑問について紹介しています。

株式会社MEBUKU
Pokke編集部
1.まず最初におみくじの種類を知ろう
おみくじは神社仏閣によっていろいろな種類があります。
一般的なのは「みくじ箋」という折り畳まれたおみくじを直接選ぶものや「みくじ棒」と呼ばれる細長い棒の入った角柱。
あるいは円柱形の筒状の箱を振り、小さな穴から一本取り出し、棒に書いてある番号と同じ番号のみくじ箋を受付などから受け取る方法などがあります。
その他に安産の信仰でうさぎの焼き物に入っている「うさぎおみくじ」や馬の人形がくわえた「お馬みくじ」。
また、6色のマッチ棒で赤がでたら大吉の「おみくじマッチ」や貴船神社では境内の霊泉に浮かべると水の霊力によって文字が浮かんでくる不思議なおみくじなど。
全国各地にはゲゲゲの鬼太郎おみくじなどこれまでにないユニークなおみくじがあります。
2.おみくじの起源は?
このようなおみくじの発想はどのようにして出てきたかと言いますと、昔は後継者選びや 国の祭事、吉凶や勝敗など重要なことを決めるため神様や仏様のご意見を伺う方法の一つとして用いられました。
人間の判断ではなく神仏から判断していただき決定するということで利用されたのです。
その例として戦国時代の九州地方で、戦の日取りや戦い方を決める方法としおみくじが用いられていたことが知られています。
個人の吉凶を占うようになったのは鎌倉時代初期からで、その後平安時代に天台宗比叡山元三慈恵大師良源上人が考案しました。
個人の運勢を占う目的のものが一般的になったのは江戸時代に入ってからで、現在のおみくじは6つの神社で製造され、その中の1社である二所山田神社の21代目宮司・宮本重胤氏が考案したおみくじの70%全国で利用されています。
3.おみくじは持ち帰る?結ぶ意味や理由を紹介
おみくじを引いた後に境内の木の枝や枝が折れないよう2本の柱の間に棒や縄を渡したみくじ掛というものにおみくじを結ぶ習慣があります。
おみくじを結ぶということは、神仏と縁を結ぶとか恋愛などの縁を結ぶ、また凶のおみくじを引いた時には利き腕と反対の手で結べば凶を吉に変えることができるなどの言い伝えがあります。
都合の良い方に解釈したいことから言い伝えられ利用されていますが、明確な意味や理由はありません。
大吉のおみくじは結ぶの?
おみくじを引いて大吉がでたら、そのあとおみくじをどうするか判断に迷うことがありますが、大吉のおみくじは必ず結ばなければならないということは特に決まっている訳ではありません。
人によっては大吉が実現するように境内にある木などに結ぶこともあるでしょうし、大事な人に見せるために持ち帰ることもあるでしょう。
また、実現するのを楽しみにひそかにお守りのように財布などに入れたりして大吉の運が離れないように持ち歩くこともあり、結ばなくても問題はありません。
おみくじは持ち帰るべきなの?
おみくじを引いたあとで神社仏閣によっては枝に結ぶことを禁止する看板があり、おみくじを結ぶみくじ掛もなければ持ち帰らざるを得ませんが、一般的にはおみくじを引く周囲に結ぶ場所があります。
しかし、引いた後のおみくじは必ず結ばなければならないとか、持ち帰らなければならないということは決まっておりません。
おみくじに書かれている内容をしっかり読み返すため、書かれている言葉や内容を忘れないようにするために持ち帰る人もおり、その人の判断で良いです。
最後に
おみくじは運試しのような一喜一憂するくじ引きと違い、神様や仏様からのメッセージとして、これからの健康や愛情などの運、心配事に対する今後を占うために引き、その内容を参考にするということが大事です。
おみくじには、いろいろな内容が書いてあります。その中から自分に必要な励ましやアドバイスを見つけ、これからの生活や生き方に参考にすることもできます。
おみくじを単なる吉凶を占うだけと考えるか、アドバイスとして生かすためか、またおみくじを結ぶも持ち帰るのも本人の気持ち次第です。
シェアしよう
世界のブログ
一覧で見る世界の音声ガイド
一覧で見る世界のホテル
一覧で見る共有
https://jp.pokke.in/blog/8175