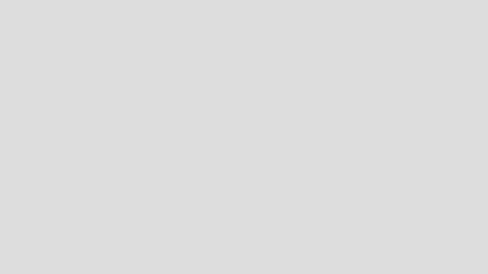美しき桜で有名な六義園でデートしよう。見どころポイント7選
公開日:2021.12.08 更新日:2023.01.05

しだれ桜で有名な六義園について知りたいと考えていませんでしょうか。この庭園は1702年に柳沢吉保という川越の藩主に作られました。現在は国から特別景勝として指定されていて、非常に美しい庭園なので重要文化財になっています。
重要文化財とされているのは、都内では浜離宮恩賜公園や小石川後楽園、そしてこの六義園だけです。この庭園の特徴として特に和歌の庭として有名です。
今回の記事では、そんな六義園についての歴史や見どころを紹介しています。自然派デートにもおすすめスポットですので、ぜひ参考にしてください。

株式会社MEBUKU
Pokke編集部
1.六義園の歴史やしだれ桜について

この庭園ですが、柳沢吉保が5代将軍綱吉から拝領された土地に造りました。5代将軍綱吉は1709年に亡くなられています。
普通、このようなときは将軍に土地を返すのですが、吉保がこの庭園を非常に気に入っていたものですから、ずっと柳沢家で別荘として使っていました。
そして明治政府のものになると、ここの手入れを怠って荒れ放題の庭園になってしまったんです。それを見た三菱財閥創設者の岩崎弥太郎氏がこの庭園を含めてこの辺一帯12万坪を買いました。
岩崎家は自社の福利厚生のためでなく、プライベートでこのお庭をお使いになり、そして、岩崎家は新しく庭園用の石を全国各地から持ってきたりして六義園を整備して、再び綺麗な状態に戻しました。
昭和13年にこの美しい庭園を、自分たちだけで楽しむには申し訳ないということで東京市に寄付しました。
この庭園は戦争で焼けてしまった部分も多いんですが、入り口付近に見える白い蔵は岩崎家が建てた蔵で、当時のまま残っています。
六義園のしだれ桜について
六義園は江戸時代の大名庭園で回遊式庭園と呼ばれています。中央に池をほって、その池の周りに植物や樹を植えてその周りを歩きながら、変わっていく景色を楽しむのが回遊式庭園です。
ちなみに京都に多い日本庭園は、鑑賞式といって室内に座って庭を眺める様式です。ここでは池を中心に時計回りに歩いていくコースが一般的な眺め方になっています。
門をくぐって正面に見える大きな木がしだれ桜です。3月下旬、普通の桜よりも早い時期に見頃を迎えます。なぜしだれ桜というのかといいますと、枝先の成長が普通の桜よりも早いんです。
自分の枝で支えることができないから、枝先が地面に向かって垂れるようになり、しだれ桜と名前が付いています。満開時には薄紅色の花が滝のように見えるのでとても美しい桜です。
2.デートの参考に!六義園の見どころポイント7選
2-1 デートでの見どころ①「出汐の湊(でしおのみなと)」
六義園|出汐湊(でしおのみなと)からの眺望 http://t.co/mGtAfWvcTD pic.twitter.com/A0EyuqXrKm
— 小川 洋 (@OgawaHiroshi_) 2013年9月29日
そのまま歩いて行くと、正面に大きな池が見えます。池の中央に見える大きな島が中の島といいます。島は土が盛ってあって、2つの山のようになっており、右側の少し大きい山が脊山(せやま)、左側のすこし小さい山が妹山(いもやま)といいます。
これは古い言葉で、背とは男性、妹とは女性のことです。この2つの山で夫婦を表しています。徳川家にとって、もっとも重要な事は子孫繁栄、つまり次の将軍を継ぐ元気な男の子が生まれることです。
その願いが込められているのが、この夫婦の仲の睦まじさを表した妹山と脊山なのです。
2-2 デートでの見どころ②「玉藻礒(たまものいそ)」
六義園、蓬莱島と吹上茶屋。#六義園、#蓬莱島、#吹上茶屋、#観光 pic.twitter.com/55BBedfPuh
— kazutada-k (@kazutadak) 2015年9月29日
出汐の湊から少し左手に歩いた地点、玉藻礒と名付けられたここも園内の美しい景色が望めるスポットがあります。正面の池に小松を乗せた小さな岩があり、蓬莱島と名付けられたこの岩は神仙思想をテーマとした石組みの一種で、典型的なアーチ型の島です。
蓬莱とは、古代中国で東の海上にある不老不死の仙人が住んでいるとされていた秘境のことで、この蓬莱島はそれをイメージして作られました。
蓬莱島の奥、中の島のよこに見える細長い石を臥龍石といいます。臥龍とは竜が伏せているという意味ですが、その名の通り、竜が伏せているような形になっています。
これは柳沢吉保の時代のものではなく、明治に入ってから岩崎家が置いたものです。向こう岸の木々が池に映り込んでおり、実はこの庭園はこの木々の映り込みを計算されて作られているのです。
2-3 デートでの見どころ③「滝見茶屋(たきみちゃや)」
【六義園】可愛らしい薄いブルーのあじさい「シチダンカ」が滝見茶屋で皆さんをお出迎え。 pic.twitter.com/ntPOVju0HU
— 都立庭園 園長の採れたて情報 (@ParksTeien) 2017年5月31日
池沿いに左手方向に歩いて行くと橋が見えてきます。その手前、左手の奥のほうに休憩スペースのような建物があります。この建物は岩崎氏が作った滝見茶屋といいます。滝というほどでは無いのですが、庭園のなかの滝を縮図として作った滝を見るためのスポットです。
この滝の流れる景色は和歌山の景色だと思ってください。和歌山の奥深い山の中の滝を連想して作っています。そしてこの水の流れは和歌山の紀の川をイメージしています。これは縮景といって、大きな景色を小さく再現したものです。
2-4 デートでの見どころ④「吹上松(ふきあげのまつ)」
【都立9庭園】六義園 – 吹上松 / 築庭当時から植えられていた由緒ある松(アカマツ)。 pic.twitter.com/he6cHLk2
— 青信号 (@elmo_FX) 2012年12月27日
対岸に移るとひときわ立派な松の樹があります。この松は庭園ができたころから植えられているこの庭園の主ともいえる存在です。つまり、樹齢300年にのぼり東京のなかでももっとも古い松の一つです。これはアカマツで、海に生える松です。
もうひとつクロマツという山に生える松もありますが、アカマツは葉が柔らかいので見分けることができます。ここは吹上の浜の吹上の松と名付けられています。
大名庭園には必ずと言っていいほど松が植えられています。将軍や大名達は松が大好きでした。一年中緑を絶やすことがなく力強い印象を与えるからです。
2-5 デートでの見どころ⑤「ささがにの道」
ささがにの道 pic.twitter.com/WC893Jx8Gb
— ベオ@魔猫 (@130w_AUC) 2017年5月5日
ささがにのみちと呼ばれる細い道が見えますでしょうか。ささがにとは蜘蛛の古い呼び名で、蜘蛛の糸のように細く長い道だからそう呼ばれています。また、蜘蛛の糸のように和歌の文化が細く長く、永遠に続いて欲しいという思いも込められています。
2-6 デートでの見どころ⑥「藤代峠(ふじしろとうげ)」
藤代峠!めっちゃすごーーい\(^-^)/ pic.twitter.com/D1Cal7IHUQ
— パナシア (@panapanaland) 2017年4月23日
ささがにの道から右にそれると小高い山に登る階段が見えます。吹上の松から池沿いに進んでももう一つの階段がありますが、この山は藤代峠と呼ばれています。
頂上は園内でももっとも美しい景色が望めるスポットですので、まずは頂上まで登ってみましょう。ここは海抜35メートルの人工の山で、今でも山手線の内側ではもっとも高い山のひとつです。
池の面からは16メートル、ビルの5階の高さです。ちなみに、2011年の震災ではこの山の3分の1が崩れ、後ろの大きな楠が横に倒れました。復旧に時間はかかりましたが、今は元通りの美しい景観を保っています。
ここができた1702年にはこのあたりに高い建物はなかったわけですから、江戸城からもここからもお互いが見えたわけです。ここは園内を見渡すための絶好のスポットですから、柳沢吉保や将軍徳川綱吉も頂上のこの石に座ってこの景色を眺めていました。
2-7 デートでの見どころ⑦「渡月橋」
六義園「渡月橋」 pic.twitter.com/unocKLGdQg
— Oh-taku (@one_for_elena) 2017年5月6日
園内で一番高い山、藤代峠を降りて時計回りに池沿いを歩いて行くと、2枚の石でできた橋、渡月橋があります。ここを渡ってみるのもいいですが、橋から見て中央の池とは反対方向、芦部茶屋跡に行きましょう。この橋を含めた園内の景色こそが、六義園のなかでももっとも美しい景色の一つです。
さて芦部茶屋跡が重要なのは、ここに来てあの橋を眺めるということが、ここを造った柳沢吉保の設計に組み込まれているからです。あの橋は渡月橋と名付けられています。
3.冬の六義園を訪れました!その時の写真を紹介
冬の六義園の写真1枚目

入り口です。
冬の六義園の写真2枚目

しだれ桜です。冬なので桜は咲いていません。
冬の六義園の写真3枚目

雪がまだまだ残っています。
冬の六義園の写真4枚目

冬の六義園の写真5枚目

一休みできる場所も。
4.六義園の基本情報
■六義園の営業時間
9:00~17:00
■六義園の定休日
年末年始
■六義園の入場料
大人300円
■六義園の最寄駅
JR山手線・東京メトロ南北線「駒込駅」より徒歩7分
■地図
5.六義園の口コミについて
庭園好きの人におすすめされて
朝から六義園へ。
暑かったので冷抹茶。 pic.twitter.com/dckWhTFpsh— 圭 (@k_dateko) 2016年6月11日
そういや桜でおすすめは東京の六義園ってところシダレサクラ!ライトアップされててめちゃくちゃ綺麗よ!一度行った方がいいかも感動しますよ pic.twitter.com/evzAskoOae
— 🌻セト(瀬戸) (@foufoy_153) 2017年4月21日
六義園は見頃なのでおすすめですよー pic.twitter.com/gkD6reyWMp
— にいかわ (@nkw5oxo5) 2014年3月29日
6.まとめ
いかがでしたでしょうか。六義園はデートにもおすすめしたい観光スポットです。美しいしだれ桜は本当に息をのむほど綺麗であり、一度は見てみる価値があります。
また、桜だけでなく、紫陽花などの花も見どころですので、ぜひ六義園を楽しんでください。
シェアしよう
和歌山のブログ
一覧で見る和歌山の観光施設
一覧で見る共有
https://jp.pokke.in/blog/9325