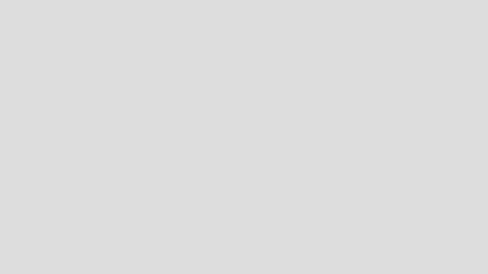正しい紹興酒の飲み方とは?種類や豆知識、歴史までも徹底紹介
公開日:2021.11.07 更新日:2022.11.25

みなさんは紹興酒をお飲みになったことはあるでしょうか。脂っこい中華料理との相性が抜群なので、本格中華のフルコースなどで出されると、おいしさのあまりつい飲み過ぎてしまった…という人も少なくないでしょう。
そこで今回の記事では、フランスのワイン、日本の純米吟醸酒と並んで「世界三大美酒」と呼ばれている紹興酒について、原料や醸造方法、色や味の特長、おいしい飲み方などをまとめてみました。

株式会社MEBUKU
Pokke編集部
1.紹興酒とはどんなお酒?
紹興酒と蒸し鶏
うっ まっ! pic.twitter.com/bnfvmBH8Bw— 酒クズコージ (@iwbk) 2018年9月19日
紹興酒とは、黄酒の一種で、上海の南に位置する浙江省の紹興市付近で造られているお酒です。中国の酒は原料と製法により、大きく次の3つに分類されます。
穀物で造る蒸留酒の「白酒(パイチュウ)」、果実で造る醸造酒の「紅酒(ホンチュウ)」、そして米で造る醸造酒の「黄酒(ホアンチュウ)」です。
原材料にはもち米を使用していますが、亜熱帯気候に属する紹興は昔から良質なもち米の名産地であり、なおかつ水がきれいなことで有名な鑒湖(かんこ)という湖もあるため、古来より黄酒の名産地となっていったわけです。
なお、日本で出回っている紹興酒には台湾産が多いのですが、本来なら紹興エリア以外で造られた黄酒は紹興酒と名乗れません。
フランスのシャンパーニュ地方で造られたスパークリングワインでなければ、シャンパンと名乗れないのと同じです。
2.紹興酒にまつわる歴史と慣習とは
紹興市がある浙江省では、古代黄河文明の時代から酒が造られていたことが書物に記されています。
紹興酒が歴史に初めて登場したのは今から2500年近く前の春秋時代で、それ以降も中国のいろんな書物の中に紹興酒が登場します。
紹興の特産品として本格的に酒造りがスタートしたのは10世紀後半からで、当時の紹興酒は「蓬莱春酒」と呼ばれ、高貴な方への贈物として特別扱いをされていました。
酒を出荷する中秋の時期には都で祭事が行われ、それを見たさに見物客が大勢集まってきたそうです。
また、かつての紹興では女の子が生まれると、誕生3日目を祝って贈られた米を使って酒を醸し、かめに入れて地中に埋め、娘が結婚する日に掘り出して嫁入り道具として持たせたり、祝いの酒として客に振る舞う慣習があったと言われています。
3.紹興酒の種類と色に関する豆知識を紹介
紹興酒はもち米、麦麹、水を主原料としており、その他に加える材料と熟成期間の違いなどによって、大きく次の4種類に分けられます。
①元紅酒
②加飯酒
③善醸酒
④香雪酒
①の元紅酒はすべての紹興酒の基本であり、中国では最もよく飲まれていますが、日本では一般的に紹興酒と言えば②の加飯酒のことを指します。
加飯酒は元紅酒よりも米と麹を1割多く使用し、醸造後最低3年間熟成(陳醸)させたものです。
紹興酒と日本酒では原材料(米)や醸造方法などで共通点は多々あるのですが、日本酒が透明であるのに対して、紹興酒は濃厚な琥珀色をしています。
その理由としては、アミノ酸の量が日本酒より数十倍も多く、このアミノ酸が熟成期間中に糖と化学反応を起こして褐色物質を生み出すためと言われています。
ただ、今日では市販品の多くにカラメルが添加されており、その色味が影響していることが多いようです。
4.熟成期間別・紹興酒の味の違いについて
アルコール度数が高そうに見える紹興酒ですが、実際は焼酎より低く、ワインや日本酒より少し高い程度です(18〜19度)。
主な市販品は、熟成期間によって3年陳醸から20年陳醸に分かれ、味わいもそれぞれ少しずつ異なります。
日頃中華料理店などで目にする機会が多く、値段もお手頃な3年陳醸と5年陳醸は、甘味よりも酸味の方が強く感じられます。
そのため飲み口はドライで力強く、脂っこい料理や香辛料を効かせたスパイシーな料理には最適です。8年陳醸から12年陳醸クラスになると、酸味が幾分弱まって角が取れ、口当たりがずいぶんと柔らかくなります。
相対的に甘味と旨味が立ってくるため、発酵調味料である醤油や味噌をベースにした料理によく合います。
そして15年陳醸や20年陳醸クラスともなると、色・香りともに濃厚さを増し、口当たりも上品かつまろやかで、酸味はほとんど感じられなくなります。
その分複雑で深みのある旨味が口の中に広がるため、素材そのものの味を楽しむような料理に合わせたくなります。
5.こんなに美味しい!紹興酒の飲み方をいろいろ
紹興酒の飲み方①「ストレート」
中国では、そのままストレートで飲むのがごく一般的です。紹興酒ならではの芳醇な香りと、まろやかな旨味を最も感じ取ることができます。
特にまろやかさと旨味が増した12年陳醸以上の熟成酒については、一杯目だけでもぜひストレートで味わってほしいものです。
なお、温度は本来常温で飲むのがおすすめですが、独特な風味が少し苦手な方には、冷蔵庫で冷やしてから飲むと香りが抑えられて飲みやすくなります。
紹興酒の飲み方②「オンザロック」
ロックにすると温度が冷たくなると同時に重厚さも少し和らぐため、辛味の強い料理などには合わせやすくなります。
大きめのグラスにクラッシュアイスを入れて注ぎ、カットレモンを添えるのも一興です。
紹興酒の飲み方③「ソーダ割り」
独特な香りや風味が苦手な方、アルコールに弱い方には、ソーダで割った「上海ハイボール」はいかがでしょう。
レモンを少量絞るとより爽やかさが増して飲みやすくなります。
紹興酒の飲み方④「カクテル」
烏龍茶で割る「ドラゴン・ウォーター」、紹興酒2:梅酒1でブレンドする「梅ロック」、ジンジャエールで割ってスライスレモンを添える「香港フィズ」などがポピュラーです。
紹興酒の飲み方⑤「ホット」
紹興酒の香りが好きな方には、人肌くらいのぬる燗がおすすめです。華やかな香りがグラスから立ち上り、口当たりもまろやかさを増します。
なお寒い冬には、千切りにした生姜を2、3本浮かべると代謝が上がり、体も心もポカポカと温まりますので、冷え性の方はぜひお試し下さい。
6.まとめ
最後に一つだけ補足です。日本では、紹興酒というのは氷砂糖やザラメを入れて飲むもの、と思い込んでいる人がいるようですが、これは正式な飲み方ではありません。
酒は嗜好品なので楽しみ方は人それぞれですが、これから紹興酒を飲んでみようという方には、まずはそのままの味を体験されることをおすすめします。
シェアしよう
共有
https://jp.pokke.in/blog/7951